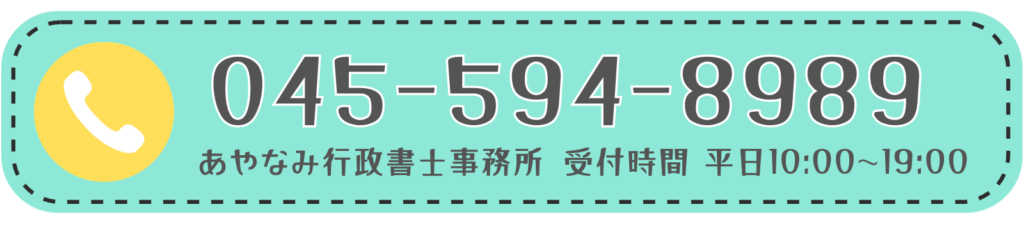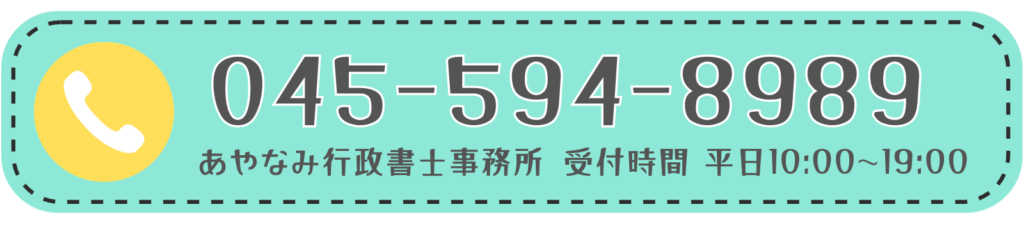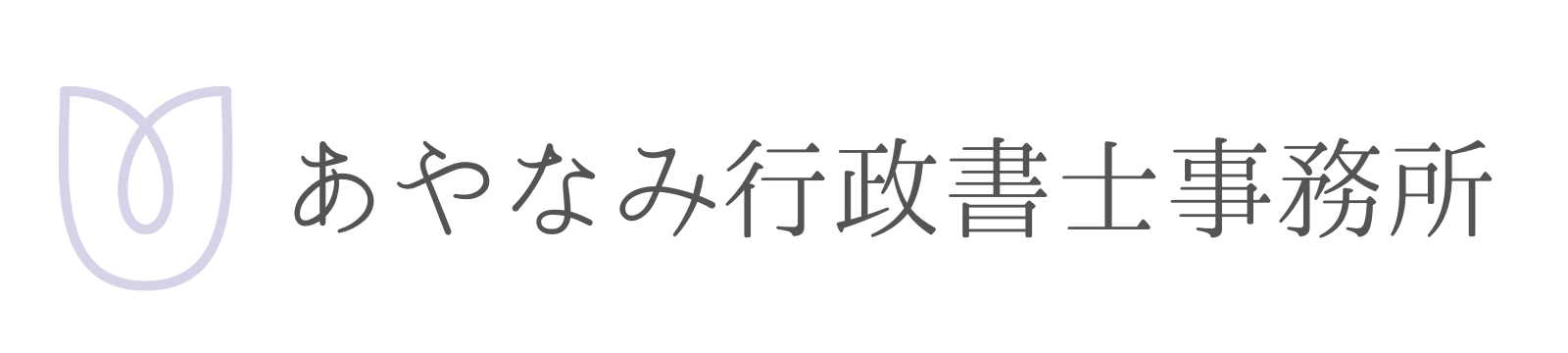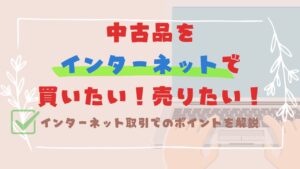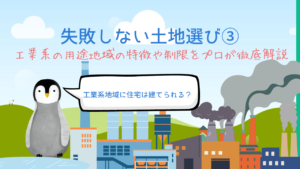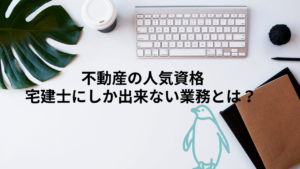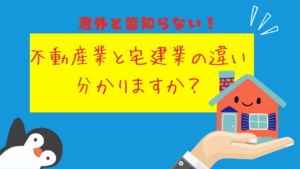皆さんは家や土地などの不動産を実際に購入する際は、さまざまな情報を事前にチェックする必要がありますよね。
不動産取引の流れや相場、住環境や予算、住まい、担当する不動産会社など調べておきたいポイントがいろいろあると思います。
その中でも今回は、特に大切な住環境のポイント「用途地域」について解説をしていきたいと思います。
用途地域とは
 タッケン
タッケン将来マイホームを買うなら3階建ての氷のおうちを建てたいな~。
夢のマイホーム計画だね。実現するためにはまずはエリア選びが重要です。そのエリア選びの参考にしたいひとつの情報が、今日お話しをする用途地域のことなんですよ。
家を建てるための土地を探している場合や、土地付きの戸建てを購入して将来建て替える予定がある場合は、土地の用途地域を確認しておかないと、将来建てたい家が建てられない!なんて場合もあるので注意が必要です。
それは何故かと言うと、用途地域が指定されている地域は建築物の用途の制限に合わせて、建築物の建て方のルールも決められているからです。
例えば、土地の面積と建物の床の面積の比率(容積率と言います。)や道路の幅に見合った建物の高さなどです。
そのように特徴のある13種類の用途地域うち今回の記事では住居系に焦点を当てて、ひとつひとつ一緒に確認していきましょう。
住居系の用途地域とは
第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。高い建物や騒音を出すような用途の建物は建築できません。
名前の通り、高さ制限があります。
市町村によって異なりますが、10mまたは12mの高さ制限があり、また軒の高さが7mを超えるか3階以上の建築物で、条例で指定する区域に建つ建物は日影規制の適用対象です。
戸建住宅や共同住宅のほかは、小中学校や交番のような公共施設、診療所や寺院、老人ホームのような福祉施設等は建築可能です。
不特定多数が集まるような施設は、基本的には建築できないので閑静な住環境を保つことができます。
その一方で店舗兼住宅のような例外を除いては店舗の建築は出来ません。
コンビニやドラックストアのような小規模なものも不可です。
このため生活に必要なお店が、家からやや遠くなる可能性はあります。



第一種低層住居専用地域っていろいろと制限が多いんだね~。
それもすべて良好な住環境を守るために必要なことです。
それを踏まえて、実は土地価格や戸建住宅の資産価値が高いのもこのエリアの特徴です。
第二種低層住居専用地域
主に低層住宅の良好な住環境を守るための用途地域になります。
第一種低層住居専用地域との定義の違いは「主に」があるがないかのわずかなものです。
第一種低層住居専用地域の建てられるものに加えて、150㎡以下、かつ店舗部分が2階以下の店舗は建築可能です。
ただし、その用途は日用品の販売、理髪店や美容店、クリーニング店などと限定的です。
コンビニなどの店舗が建築できることが、第一種低層住居専用地域との大きな違いなのです。
- 診療所やごく小規模な店舗が限界の第一種・第二種住居専用地域のため、大型のショッピングセンターや総合病院などが近所にない可能性があります。
- 高さ制限があることから地域内で3階建てを建築することは難しくなっています。
- 商業系の地域と隣接していた場合、静かで良好な住環境が達成できない場合もあります。
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域です。
主に3階以上のマンションをはじめとする、中高層の集合住宅を建築していく動きがみられます。
建築できる建物にやや制限が多く、活気を求めるというよりも、落ち着いた暮らしを提供するエリアであると言えます。
第一種中高層住居専用地域は、住居としての環境を保つことが目的のため、中高層マンションや戸建て住宅、住環境を損なわない図書館や学校などは建設することができます。
また、完全な住居のみの建物だけではなく、店舗兼住宅や、業種によって2階以下、かつ150㎡以内や500㎡以下の店舗も建築が可能となります。
- 大学、高等専門学校、専修学校
- 病院
- 老人福祉センター、児童厚生施設
- 店舗、飲食店(規模500㎡以内、地下含め2階以下のみの物品販売店か飲食店に限る)
- 自動車車庫(床面積合計300㎡以内、3階以下)
- 銀行の支店、損害保険代理店、不動産会社の店舗、税務署、警察署、保健所、消防署など
- 規模の大きい店舗
- 住環境を損なうパチンコ店やボーリング場などの遊戯施設
- 工場
- 危険物を取り扱う施設
- 事務所(50㎡以下の住居兼用事務所のみ可)



第一種中高層住居専用地域だと、なんと大学が建てられるんだ!
そうだね。 大学の建設は可能であるものの、オフィスビルは建てることが出来ないから、大きな会社などが建築されることがないのも特徴のひとつ。タッケンも覚えておいてくださいね。
第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域です。
住宅と公共施設や小中規模の店舗が混在し、それなりに面積が大きめの店舗や飲食街が並ぶなど、第一種中高層住居専用地域よりも制限が緩和されています。
都市部の駅前にはあまり設定されず、少し駅から離れた立地に多いことが特徴です。
中高層住居専用と言うだけあってマンションやアパート経営に適しており、物件も多数みられます。
幼稚園や小・中学校・高校も近くにある場合が多く、ファミリー層に人気がある地域です。
- 第一種中高層住居専用地域内で建てられるもの
- 床面積1500㎡以内で2階以下の店舗や飲食店、事務所などの施設
- パチンコ屋、カラオケボックス、劇場、映画館、ボーリング場、プールなどの遊戯施設
- 300㎡を超える駐車場
- 倉庫業の倉庫
- 工場
- ホテルまたは旅館
- 自動車教習所
- 15㎡以上の畜舎
- 3階以上の階への店舗や飲食店の建設
- 2階以上、かつ床面積が1,500㎡を超える事務所等



第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域は、どちらが暮らしやすいんだろう?
う~ん・・静かに暮らしたいのであれば、第一種中高層住居専用地域。
生活の便利さで考えるならば、第二種中高層住居専用地域という感じかな。自分のライフスタイルに合わせて選んでいく感じですね。
第一種住居地域
住居の環境を保護するための地域です。
住居をメインとしつつも、比較的大きめな建物の建造が認められています。
駅周辺の地域が多く、商業施設が立ち並びます。
住環境がメインでありながらも、賑やかさのあるエリアです。
利便性の良さが魅力ですが、日当たりや日陰などに関する制限の内容があまり厳しくないため、戸建てやマンションが密集しているエリアが多くなり、住居専用地域に比べると日当たりの悪い場所が目立つこともあります。
また、駅から近いことや通勤しやすいなどの利便性が高い地域では、思った以上に通行人や交通量が多いこと、音が気になる場合があることも念頭においておきましょう。
- 第二種中高層住居専用地域で建てられるもの
- 寄宿舎、下宿、兼用住宅
- 3,000㎡以下の店舗や事務所、3,000㎡以下の運動施設や展示場等、公共施設、病院、学校等
- 周辺環境を悪化させる危険性がなく、床面積が50㎡以下のものであれば工場も可能
第二種住居地域
住宅と店舗やオフィスなどの共存を図りながら、主に住居の環境を保護する地域です。
住宅や商業施設、工場などが混在する市街地のうち、住宅の割合が多い地域が指定されています。
交通の便が良く、大規模な商業施設や娯楽施設もあるため、便利な生活を送ることができます。
幹線道路沿いや郊外駅前が指定地域となる確率が高く、必然的に車の通りが多い場合があります。
騒音や排気ガスの影響で、年中窓は締めっぱなしだったり、洗濯物をベランダに干せないなどの状況に悩まされるケースもありますので、利便性と住環境のバランスをうまく考えて検討するエリアと言えるでしょう。
- 第一種住居地域で建てられるもの
- パチンコ屋、カラオケ屋、ホテル、ボーリング場、スケート場、ゴルフ場、バッティング練習場
- 150㎡までの自動車修理工場、50㎡までの作業場
- 10,000㎡以下の店舗や事務所
- 映画館や劇場など人が集まる施設
- 風俗営業を営む施設
- 住環境を悪化させるおそれのある規模の工場



たくさん覚えることがあり過ぎて、頭がこんがらがってきたよ
自分だったら将来どの地域に住みたいかなっていうのをイメージするのがオススメです。一番最初の第一種低層住居専用地域(一低)で建てられるものをしっかり覚えてからそこにだんだん追加していく感じで…。
住居系も残るところあと2つ! タッケンファイト!
準住居地域
道路の沿道としての特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
住居系の地域としては最も建物の規制が緩やかになるエリアです。
国道や幹線道路が近いため、普段から自動車移動の多い方に向いた地域と言えるでしょう。
大型の商業施設が建築可能な地域ですから、買い物に便利な環境の可能性は高いです。
車利用者にとっては生活しやすいと言えますが、大きい道路が近くにあることで子どもが通学したり、家の周囲で遊ぶ際には注意が必要です。
- すべての住居系地域で建築可能な共同住宅、学校、図書館、寺社などはもちろん、病院、大学、福祉施設
- 公共施設、店舗、飲食店などは床面積が10,000㎡以下のもの
- 10,000㎡以下の麻雀店、カラオケボックス、パチンコ屋
- 客席200㎡以下の映画館、演芸場
- 床面積が150㎡以下の自動車修理工場
- 3階以上または床面積が300㎡を超える営業用倉庫
- キャバレーやナイトクラブ、風俗店
- 危険性や環境を悪化させる恐れのある工場
田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する地域です。
「市街化区域」のなかでも農地や緑地が多く緑豊かな地域です。
2018年4月1日に新設されたこの地域ですが、日本の高度経済期に都市周辺地域の宅地化が進む一方、緑地の価値が見直され農地を保全する地区が設けられました。
都市部の農地はバブル期に土地価格上昇による固定資産税の負担増しのため、税負担の軽い宅地化へ転用が進みました。
そこで生産緑地法の改正によって宅地化せずに保全する農地の税制措置を行ったのです。
2022年は、その生産緑地法による都市部農地税制優遇措置の終了期限に当たるということで、生産緑地が一斉に解除されてしまうと地価に影響を与える懸念がありました。
しかし、国がこの問題に対しさまざまな対策を講じていた結果、税金の優遇措置の10年延長を選ぶ土地主が多かったため、今のところ土地価格の大きな暴落は発生していません。
- 低層住居地域で建てられるもの
- 150㎡以下の店舗、または農産物直売所や農家レストランは500㎡以下のもの
- 農作物を生産、集荷、処理、貯蔵などと行う倉庫や作業場(2階以下のもの)
- 危険性がなく環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場や、農機具の収納施設



田園住居地域は、将来農業をやってみたい人とかにオススメなのかな。
そうですね~農業ももちろん、農業を活かした直売所やレストランといった多角的な経営が出来るように、工場や倉庫の規制が住居系の中では最も緩いエリアとなっています。
まとめ 用途地域の特徴を理解して有効な土地活用を
今回は、8種類の住居系用途地域について解説をしていきました。
自分が将来住みたい地域のイメージや今住んでいる地域の特性がよく分かっていただけたかと思います。
ただし用途地域は細かく指定がされており、購入した土地の隣の土地が実は別の用途地域だったという可能性もあります。
用途地域については指定されたものがネットに公開されていますので、検討している都道府県や市区町村の自治体から確認してみるとよいでしょう。
また、検討している土地について詳しく知りたい場合は、やはり不動産のプロに相談することをお勧めします。
弊社でも、エリアによって周辺環境や建築条件などについてご説明させていただきますので、気になる土地やエリアがある際は、ぜひお声がけください。
次回は、商業系、工業系の用地地域についていっしょに学んでいきましょう。


この記事を見て参考になったという方は、私のYouTubeチャンネルやX(Twitter)もフォローいただけると嬉しいです。
お酒の販売・製造免許や宅建業免許申請手続き等に関するご相談がございましたら、あやなみ行政書士事務所へご相談ください。
>>こちらのリンクからメールのお問合せフォームに飛びます。
- スマートフォンの場合は以下の電話番号ボタンのタップで電話がつながります。
- お問い合わせ内容により、有料相談(30分5,500円)となる場合がございます。
- ご相談前に、会社名・担当者名等をお伺いいたします。